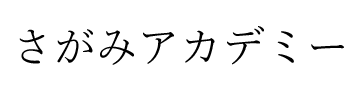順不同
講師紹介

| 講 師 | 後藤 幸良 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学学芸学部 日本語日本文学科 教授 |
| 経 歴 | 1958年 岐阜県生まれ。東北大学大学院博士課程修了。博士(文学)。新潟県立高校教諭、新潟大学人文学部助手、長岡工業高等専門学校助教授を経て、現在相模女子大学学芸学部教授。専門は平安朝文学。著書に『紫式部 人と文学』(勉誠出版 2003年)、『平安朝物語の形成』(笠間書院 2008年)、『伊勢物語と四季』(武蔵野書院、2023年)などがある。 |
講師紹介

| 講 師 | 春山 純一 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学非常勤講師 |
| 経 歴 | 理学博士(京都大学大学院)。JAXA宇宙科学研究所/総合研究大学院大学 助教。会津大学特任上級准教授。東海大学客員准教授。専門は月惑星科学・探査。月の縦孔発見の報告など数多くの学術論文がある。著書に、「人類はふたたび月を目指す」(光文社)、「月の縦孔・地下空洞とは何か」「月の科学に挑戦」「速報! JAXA探査機はやぶさ2号機 小惑星リュウグウに到着する」(以上ロビー出版、アマゾン/キンドル電子書籍)などがある。 |
講師紹介

| 講 師 | 﨑山 みゆき |
|---|---|
| 肩 書 | 株式会社自分楽代表取締役、一般社団法人日本産業ジェロントロジー協会代表理事、横須賀市文化振興委員、東京都「東京セカンドキャリア塾」講師・企画 |
| 経 歴 | 1984年 相模女子大学短期大学部国文学科卒。サンフランシスコ大学学術博士・桜美林大学国際学研究科修士。元静岡大学大学院客員教授。産業ジェロントロジー(加齢学)の第一人者。個人事業主の講師、社会人大学院生を経て法人設立。中高年に特化したキャリア開発を企業・自治体・大学などで全国展開をしている。著書「40代・50代からの働き方」(日経BP)「シニア人材マネジメントの教科書」(日本経済新聞出版社)など。取材 産経新聞・日経産業新聞・テレビ東京など多数。 |
講師紹介

| 講 師 | 宮崎 大祐 |
|---|---|
| 肩 書 | 映画監督 |
| 経 歴 | 大学を卒業後、フリーの助監督として活動し、2011 年にデビュー。以後故郷である神奈川県大和市を舞台に数々の映画を制作してきた。代表作には『大和(カリフォルニア)』、『TOURISM』、『#ミトヤマネ』などがある。 |
講師紹介

| 講 師 | 名和田 竜 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学非常勤講師・東京国際工科専門職大学非常勤講師 |
| 経 歴 | 広告代理店にて数々の成功企画を手掛けた後、マーケティング・経営戦略を専門領域とするコンサルタントとして独立。研修講師を始め執筆・講演など幅広く活動中。マーケティング視点からの歴史をテーマにした講座等も好評。JADP認定心理カウンセラー、学術団体:戦国史研究会、日本気象学会会員。主な著書『まんがで身につく!ランチェスター戦略』(あさ出版)『しくじり企業も復活する7つの大原則』(ビジネス社)等多数。 |
講師紹介

| 講 師 | 鈴木 勝己 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学非常勤講師・早稲田大学人間科学学術院通信教育課程教育コーチ |
| 経 歴 | 担当講師は早稲田大学人間科学部、通信教育課程に所属する教員である。講師は長年、文化人類学者として東南アジア・タイのエイズホスピス寺院で調査を実施してきた。寺院の人びとは、エイズに苦しむ過酷な日常を生きながらも笑顔を絶やさない。現在、ホスピス寺院はエイズ禍を学ぼうとする人びとが訪れることができる観光地となっている。寺院の人びとの笑顔は、私たち一人ひとりが生きる意味を考えるきっかけになっている。 |
講師紹介
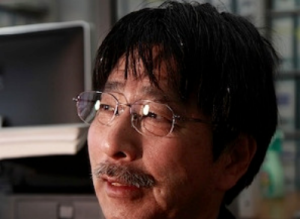
| 講 師 | 渡辺 幸俊 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学名誉教授 |
| 経 歴 | 英米演劇・映画 元「文化放送 百万人の英語 ミリオンズシアター」を10年間担当。近年はロイター社などの配信ニュースを教材化に取り組んでいる。 |
講師紹介

| 講 師 | 匂坂 桂子 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学非常勤講師 |
| 経 歴 | ①『ことわざ英語かるた』(CD、テキスト付オリジナル教材。1998年出版)を使用したかるた道場やかるた大会の開催。②オリジナル脚本に英語の歌やダンスを取り入れたミュージカルの指導、及び公演。③英語絵本の読み聞かせとアートクラフトを組み合わせたワークショップの開催、児童養護施設への訪問。④自然観察を行う活動やクッキング等各種ワークショップの企画、開催。⑤教員向け研修会。⑥教材、絵本の出版と販売。 |
講師紹介

| 講 師 | 青柳 まや |
|---|---|
| 肩 書 | 二松學舍大学文学部非常勤講師・日本体育大学体育学部非常勤講師 |
| 経 歴 | 二松學舍大学大学院文学研究科博士後期課程国文学専攻修了。博士(文学)。著書に『古代日本文学が物語る婚姻・出生伝承』(花鳥社、2020年3月)。最近の論文に、青柳まや「『先代旧事本紀』におけるタカミムスヒの役割について」(東京大学国文学会編『國語と國文學』令和5年10月号)があります。主に、『古事記』や『日本書紀』など、古代文学に記された系譜や婚姻伝承等について、その伝承が書かれた意図について研究しています。 |
講師紹介
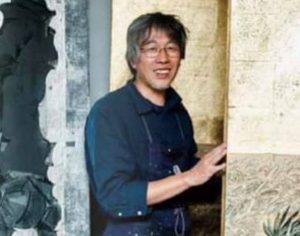
| 講 師 | ヤン シャオミン |
|---|---|
| 肩 書 | 墨絵作家 |
| 経 歴 | 1960年、中国生まれ。国立華僑大学芸術学部教員(1984~1988年)を経て1988年に来日し、1992年に和光大学芸術学専攻科修了。以降絵画の作家活動の一方、横浜美術館、練馬区立美術館、金津創作の森などで講義・ワークショップを多数実施。 |
講師紹介

| 講 師 | 小柳 茂子 |
|---|---|
| 肩 書 | 公認心理師、臨床心理士、フェミニストセラピイ“なかま”カウンセラー |
| 経 歴 | 日本大学大学院修士修了、フェミニストカウンセラーとして、女性相談に従事。東京大学ハラスメント相談室、相談員を経て、相模女子大学人間社会学部教授(2024年退職)。 |
講師紹介

| 講 師 | 金森 剛 |
|---|---|
| 肩 書 | 相模女子大学 専門職大学院 社会起業研究科 研究科長、兼人間社会学部 社会マネジメント学科 教授 |
| 経 歴 | 博士(経営学)。野村総合研究所にてコンサルティング業務に24年間従事。専門は経営戦略、マーケティング、消費者行動、ブランディング、事業・商品開発。著書に『ネットコミュニティの本質』(2009年白桃書房)、『マーケティングの理論と実際』(2012年共著、晃洋書房)、『共感ブランド』(2014年、白桃書房)、『地方創生:デジタルで救う地域社会・経済』(2023年共著、中央経済社)など。 |